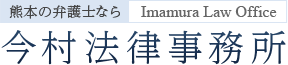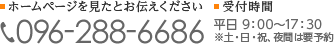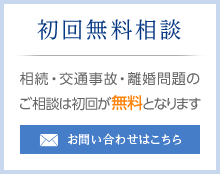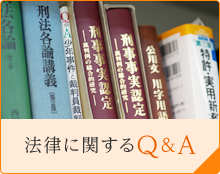売掛金の回収
2015.05.26更新
取引先に多額の売掛金があり,取引先からはいつまでたっても支払ってもらえないという相談がよくあります。商品等の売買取引が1回だけ行われるような取引の場合は,商品の引渡しと売買代金の支払いが同時履行とされることが多いため,売買代金の回収で取引先とトラブルが発生することはほとんどありません。しかし,取引先と継続的に商品を売買するときには,商品の引渡毎に代金の支払いを受けるというのではスムーズな取引ができないので,一定期間内の売買代金については,一定の期日に支払いを受けることとするのが通常です。このような売掛金は,買主の支払能力を中心とする信用の上に成り立っていますが,買主から支払いがないなどのトラブルが発生することもあります。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
投稿者: