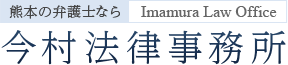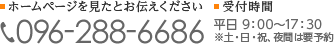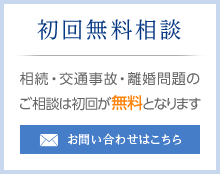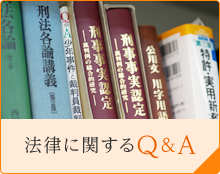貸金の時効
2015.05.18更新
業務として金銭貸付をしているような場合,債務者に請求しても時効になっているとクレームを受けることがありませんか?貸金債権の時効についてどのように考えればよいのでしょうか。そもそも貸金債権について消滅時効が完成してしまうと,貸金の返済を受けることはできませんので,多数の金銭債権を管理する金融機関等の債権管理担当者は,債権を時効にかけてしまわないように時効の起算日と時効期間等を債権管理簿に記載するなどして,債権管理を確実にし,時効期間満了日が近い場合には,確実に時効中断の措置を講じつつ中断措置の証拠を保存する必要があります。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
投稿者: