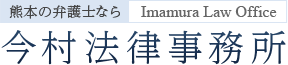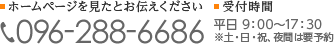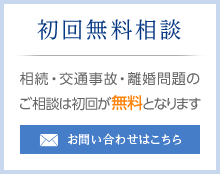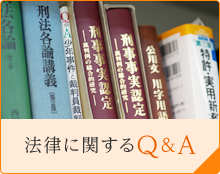遺言公正証書の件数、伸びています。
2015.06.24更新
遺言公正証書の年間作成件数が2014年に初めて10万件を突破したとのニュースがありました。日本公証人連合会の調べによると、遺言公正証書は1971年には1万5000件、1980年は約3万件、2000年は約6万件であり、この間明らかに遺言公正証書は増え続けています。これは、高齢化が急速に進んでいることに加え,核家族化や事実婚に代表されるように家族の形態が多様化したため、法律の規定とは異なる相続を望む人が増えているということも背景にあるのではないでしょうか。社会には、たとえば、「夫婦には子供がいないが、仲の悪い兄弟には財産を渡したくない。」とか「近くに住んで面倒をよく見てくれた次女に他の兄弟姉妹よりも多くの財産を相続をさせたい。」とか「内縁の妻に財産を残したい。」とか様々なニーズがあるので、遺言公正証書がこのようなニーズに応えているようです。なお、今後も遺言公正証書のニーズは増え続けると予想しており、日本公証人連合会では、遺言を確実に保管するために証書のデジタルデータ化にも取り組んでいくそうです。なお、気になる遺言公正証書の作成手数料ですが、これは遺産額で決まり1000万~3000万円の場合は相続人1人あたり2万3000円だそうです。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
投稿者: